西川嘉右衛門商店会長
| 西川嘉廣さん 西川嘉右衛門商店会長 |
| |
|
|
|
| ヨシ博物館とは? |
|||
| 第134回 | ヨシに熱風が吹いてきた |
| 2005年6月30日 菱川貞義 |
| 「熱風」という冊子のことを知っている方は、きっとかなりのジブリファンではないでしょうか。 | |
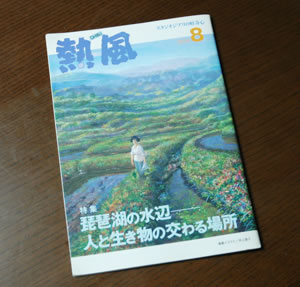 |
その冊子をヨシ博物館で発見しました。 「やはりヨシと関係があるのだろうか?」 実は2004年8月号にヨシ博士の記事が載っていたのです。副題に「スタジオジブリの好奇心」と書かれた、「熱風」のスタッフの好奇心のアンテナについにヨシ博士がひっかかったようです。 スタジオジブリから突然、ヨシ博士に電話が入ったとき、ヨシ博士はスタジオジブリのことをまったく知りませんでした。 |
| 「スタジオジブリなんか知らん」と答えたヨシ博士ですが、それでも、ヨシに関心をもった人の頼みなので、こころよく執筆依頼を受けられたそうです。スタジオジブリの方が電話の向こうで、「スタジオジブリはどういうものなのか」を必死で説明した様子が目に浮かびました。何せ「熱風」は知らなくても、「スタジオジブリです」といえば、だれでも知っていると思っていたでしょうから。 | |
「熱風」は、特集「琵琶湖の水辺ー人と生き物の交わる場所」として、「湖辺(みずべ)のヨシ原こそ人と自然のネットワークの基礎」と題されたヨシ博士のほかに、「水系としての琵琶湖」の今森光彦さん、「湖辺に住む人びとの今とむかし」の嘉田由紀子さん、「暮らしに生きていた丸子船」の牧野久実さん、「アワミの多層海(表紙の言葉)」の井上直久さんの記事を組んでいました。 |
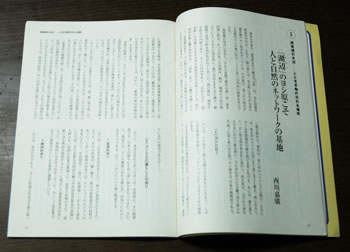 |
「琵琶湖で魅力的な場所には必ず魅力的な人の営みがある」とする編集は、さすが、スタジオジブリの好奇心だけあって、内容の濃い記事ばかりでした。 広大な小宇宙として里山で共存している生き物たちを紹介した今森さん。ネパールから琵琶湖にやって来た14歳の少女が、湖辺に住む人びとの「集落による自治的な水保全」「水への畏敬の念」に驚嘆し、世界のなかで琵琶湖の特異性や魅力を外の目で追いながら、失われつつある大切なものを教えてくれた嘉田さん。戦前、丸子船がつくられたころは、材を入手するために、船大工が必要とする木がどの山にあるかという情報を提供した、とんびや、木挽き、山師、出しの親方という職種の人びとがかかわっていて、木を切り出して雪が積もるまで放置し、雪面を利用して丸太を川辺に運び、春の雪解けで川が増水すると丸太を水中に落とすといった、くらしにちりばめられた人びとの知恵を紹介した牧野さん。表紙の絵で、多層の淡海を表現した井上さん。 そして、ヨシと人の暮らしとの係りとして、簾・衝立・障子や屋根葺きなどの実用的係り、ヨシの浄化能力から由来する破魔矢・追儺の儀式の矢・茅の輪くぐり・御葭流し・葦占・葦粽・葭松明祭り・祇園祭の芦刈山などの精神的係り、さらに機能的係りとして、水質浄化作用・生態系保全・護岸作用・景観形成に触れられた西川さん。とくに四季を通じてダイナミックに魅力を形成するヨシ原の、視覚的だけでなく、音風景として聴覚的にも重要な構成要素があることを強調されていました。最後に、新しい需要を掘り起こすヨシの新規活用法に関する研究として、滋賀県立大学・成安造形大学・京都嵯峨芸術大学を紹介し、こうした若い世代からの“熱風”が、遠からずヨシの活用に新たな展望を開くであろうと確信している、と強く結ばれています。 特集を読み、いかに自然を大切にし、自然の声をよく聞き、自然に寄り添いながらゆたかに生きてきているかがよく伝わってきました。もっと内容を読みたくなった方はヨシ博物館に出かけられたらいかがでしょうか? |
 |
(つづく) |
![]()